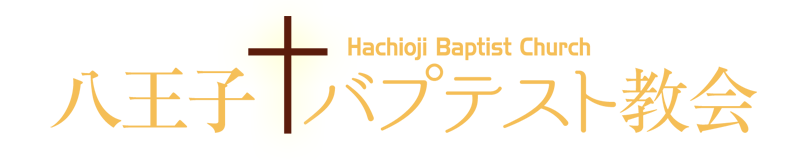み言葉を託された者:エリヤ(5)
さてアハジヤはサマリヤにある高殿のらんかんから落ちて病気になったので、使者をつかわし、「行ってエクロンの神バアル・ゼブブに、この病気がなおるかどうかを尋ねよ」と命じた。時に、主の使はテシベびとエリヤに言った、「立って、上って行き、サマリヤの王の使者に会って言いなさい、『あなたがたがエクロンの神バアル・ゼブブに尋ねようとして行くのは、イスラエルに神がないためか』。それゆえ主はこう仰せられる、『あなたは、登った寝台から降りることなく、必ず死ぬであろう』」。そこでエリヤは上って行った。使者たちがアハジヤのもとに帰ってきたので、アハジヤは彼らに言った、「なぜ帰ってきたのか」。彼らは言った、「ひとりの人が上ってきて、われわれに会って言いました、『おまえたちをつかわした王の所へ帰って言いなさい。主はこう仰せられる、あなたがエクロンの神バアル・ゼブブに尋ねようとして人をつかわすのは、イスラエルに神がないためなのか。それゆえあなたは、登った寝台から降りることなく、必ず死ぬであろう』」。アハジヤは彼らに言った、「上ってきて、あなたがたに会って、これらの事を告げた人はどんな人であったか」。彼らは答えた、「その人は毛ごろもを着て、腰に皮の帯を締めていました」。彼は言った、「その人はテシべびとエリヤだ」。そこで王は五十人の長を、部下の五十人と共にエリヤの所へつかわした。彼がエリヤの所へ上っていくと、エリヤは山の頂にすわっていたので、エリヤに言った、「神の人よ、王があなたに、下って来るようにと言われます」。しかしエリヤは五十人の長に答えた、「わたしがもし神の人であるならば、火が天から下って、あなたと部下の五十人とを焼き尽すでしょう」。そのように火が天から下って、彼と部下の五十人とを焼き尽した。王はまた他の五十人の長を、部下の五十人と共にエリヤにつかわした。彼は上っていってエリヤに言った、「神の人よ、王がこう命じられます、『すみやかに下ってきなさい』」。しかしエリヤは彼らに答えた、「わたしがもし神の人であるならば、火が天から下って、あなたと部下の五十人とを焼き尽すでしょう」。そのように神の火が天から下って、彼と部下の五十人とを焼き尽した。王はまた第三の五十人の長を部下の五十人と共につかわした。第三の五十人の長は上っていって、エリヤの前にひざまずき、彼に願って言った、「神の人よ、どうぞ、わたしの命と、あなたのしもべであるこの五十人の命をあなたの目に尊いものとみなしてください。ごらんなさい、火が天からくだって、さきの五十人の長ふたりと、その部下の五十人ずつとを焼き尽しました。しかし今わたしの命をあなたの目に尊いものとみなしてください」。その時、主の使はエリヤに言った、「彼と共に下りなさい。彼を恐れてはならない」。そこでエリヤは立って、彼と共に下り、王のもとへ行って、王に言った、「主はこう仰せられます、『あなたはエクロンの神バアル・ゼブブに尋ねようと使者をつかわしたが、それはイスラエルに、その言葉を求むべき神がないためであるか。それゆえあなたは、登った寝台から降りることなく、必ず死ぬであろう』」。彼はエリヤが言った主の言葉のとおりに死んだが、彼に子がなかったので、その兄弟ヨラムが彼に代って王となった。これはユダの王ヨシャパテの子ヨラムの第二年である。
II列王紀1:2〜17
さて、エリヤの活動の最後に近づいています。エリヤは忠実に主に従っていますが、いまだになかなか「いい仕事」が回ってきません。今回は、今は亡きアハブ王の子、アハジヤに対する裁きの宣告です。もちろん、これも生命の危機が伴うものです。
ことの発端は、アハジヤ王の転落事故です。その結果、「病気」になったと記載されていますが、これは当然、感染病でも流行り病でもなく、臓器の損傷による健康被害と見られます。しかし、当時はそのようなことを知る由もありません。そこで、この病気が治るのかを、家来に尋ねにいかせます。ただ、それはエルサレムでもなく神の預言者でもなく、エクロンに行かせます。エクロンとは、イスラエルとペリシテの領土の境界にある町で、頻繁に双方の間で領土紛争の対象になる地域にありました。エクロンの特徴は、大きなバアル崇拝の拠点があったことです。日本に例えるならば、東京近辺で言えば、成田山、川崎大師、浅草寺のような存在でしょうか。
アハジヤ王がとった行動は、ヤラべアムの時代から偶像崇拝が国教化され、アハブとイゼベルがバアル崇拝を広めた影響を考えると、自然かもしれません。しかし、これはカルメル山での対決の後です。イスラエルの人々は天の神の実力を見せつけられ、神であるのはバアルではなく、イスラエルの主であることを認めた後です。慣習とは言え、ヤラべアムの行動は言い訳が立ちません。
さて、エリヤは神の言葉を告げると、命辛々逃げ出す、相変わらずのスタイルです。当然、王からの使者が逮捕に来ますが、二度にわたり神の火に焼き尽くされ、エリヤのもとに命乞いをして来た三度目の使者とともに王のもとを訪れ、自分に託された神の言葉を告げます。
列王紀の記録の中では、これが主に取り去られて天に上る前にエリヤが行った最後の仕事弟子が、実はこの少し後に、南のユダに関してもひとつ仕事をしています。ただ、この仕事はリモートでした。
ヨラムの世にエドムがそむいて、ユダの支配を脱し、みずから王を立てたので、ヨラムはその将校たち、およびすべての戦車を従えて渡って行き、夜のうちに立ち上がって、自分を包囲しているエドムびととその戦車の隊長たちを撃った。エドムはこのようにそむいてユダの支配を脱し、今日に至っている。そのころリブナもまたそむいてユダの支配を脱した。ヨラムが先祖たちの神、主を捨てたからである。彼はまたユダの山地に高き所を造って、エルサレムの民に姦淫を行わせ、ユダを惑わした。その時預言者エリヤから次のような一通の手紙がヨラムのもとに来た、「あなたの先祖ダビデの神、主はこう仰せられる、『あなたは父ヨシャパテの道に歩まず、またユダの王アサの道に歩まないで、イスラエルの王たちの道に歩み、ユダとエルサレムの民に、かのアハブの家がイスラエルに姦淫を行わせたように、姦淫を行わせ、またあなたの父の家の者で、あなたにまさっているあなたの兄弟たちを殺したゆえ、主は大いなる災をもってあなたの民と子供と妻たちと、すべての所有を撃たれる。あなたはまた内臓の病気にかかって大病になり、それが日に日に重くなって、ついに内臓が出るようになる』」。その時、主はヨラムに対してエチオピヤびとの近くに住んでいるペリシテびととアラビヤびとの霊を振り起されたので、彼らはユダに攻め上って、これを侵し、王の家にある貨財をことごとく奪い去り、またヨラムの子供と妻たちをも奪い去ったので、末の子エホアハズのほかには、ひとりも残った者がなかった。このもろもろの事の後、主は彼を撃って内臓にいえがたい病気を起させられた。時がたって、二年の終りになり、その内臓が病気のために出て、重い病苦によって死んだ。民は彼の先祖のために香をたいたように、彼のために香をたかなかった。ヨラムはその位についた時三十二歳で、八年の間エルサレムで世を治め、ついに死んだ。ひとりも彼を惜しむ者がなかった。人々は彼をダビデの町に葬ったが、王たちの墓にではなかった。
歴代志21:8〜20
最後の最後まで、めげるようなネガティブな仕事ですね。エリヤは生涯、王たちから逃げ隠れしながら王たちの罪に対する神の言葉を伝え続けました。同じようなことをして拷問されたり殺されたりした預言者たちもいました。そう考えると、エリヤの任務とは、きついとは言えど、常に主と共に歩み、最後には主に迎え入れられるというものでした。だけれども、この地上にいる間の歩みは、決して「御国の心地す」というものではなかったはずです。
御国というのは、今のこの呪いの元にある地上で実現するべきものではなく、私たちがこの地上での寄留の日々の先に遠く仰ぎ見るものです。
これらの人はみな、信仰をいだいて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして、地上では旅人であり寄留者であることを、自ら言いあらわした。そう言いあらわすことによって、彼らがふるさとを求めていることを示している。もしその出てきた所のことを考えていたなら、帰る機会はあったであろう。しかし実際、彼らが望んでいたのは、もっと良い、天にあるふるさとであった。だから神は、彼らの神と呼ばれても、それを恥とはされなかった。事実、神は彼らのために、都を用意されていたのである。
女たちは、その死者たちをよみがえらさせてもらった。ほかの者は、更にまさったいのちによみがえるために、拷問の苦しみに甘んじ、放免されることを願わなかった。なおほかの者たちは、あざけられ、むち打たれ、しばり上げられ、投獄されるほどのめに会った。あるいは、石で打たれ、さいなまれ、のこぎりで引かれ、つるぎで切り殺され、羊の皮や、やぎの皮を着て歩きまわり、無一物になり、悩まされ、苦しめられ、(この世は彼らの住む所ではなかった)、荒野と山の中と岩の穴と土の穴とを、さまよい続けた。さて、これらの人々はみな、信仰によってあかしされたが、約束のものは受けなかった。神はわたしたちのために、さらに良いものをあらかじめ備えて下さっているので、わたしたちをほかにしては彼らが全うされることはない。
ヘブル11:13〜16、35〜40
私たちは非常に不安で先が見通せない世の中にいます。しかし、この世とは本来そのようなもので、信仰の先輩たちはいつの時代もそのような状況の中にいました。だから御国を遠くから仰ぎ見るのです。日本では、そのように安定しない世の中の現実を、「浮き世」、つまり世の中は水面を漂っている枯れ葉のように不安定だ、と表現しました。だからこそ、御国を遠くから仰ぎ見るのです。
しかし、歴史の中には所々、社会と経済がある程度のスパンで安定することもあります。そうすると、その中にいるクリスチャンたちは、自分が何者であるのかを忘れてその社会と同化してしまい、生温い信仰に陥ってしまうこともあります。ラオデキアやコリントの教会がそうであったように。
日本は、戦後から何十年もの平和で安定した経済の時代が続きました。私たちが、その継続を、「みくにをきたらせたまえ」よりも強く望んでしまっているのであれば、自らの信仰を見直す時期に来ているのかもしれません。来週からエリシャです。
 日本語
日本語